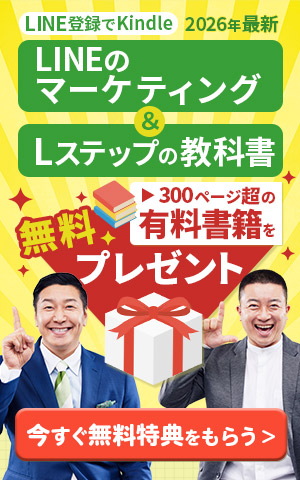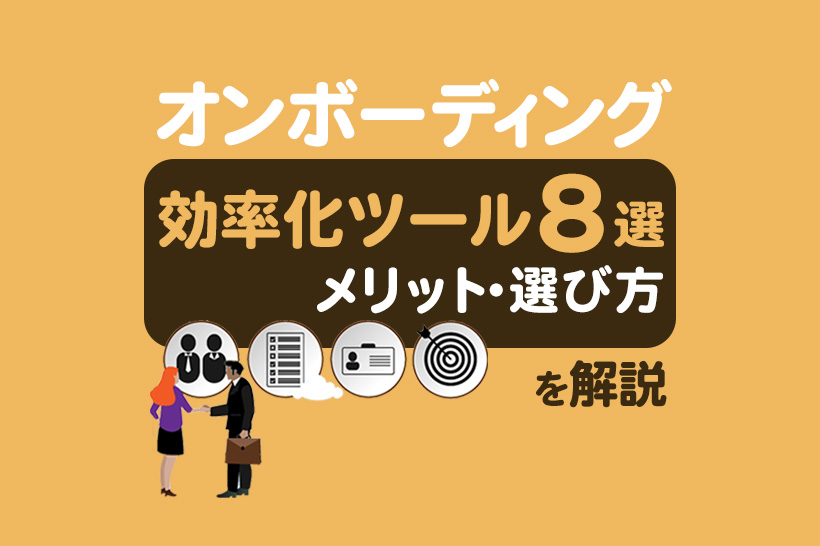
企業の成長には優秀な人材の確保と定着が欠かせません。しかし、新入社員がスムーズに業務に馴染めないまま早期に離職してしまうケースが増え、多くの企業が頭を悩ませているでのはないでしょうか?
そこで注目されているのが「オンボーディング」の仕組みです。
オンボーディングを効果的に進めるには「オンボーディングツール」の活用が不可欠です。
本記事では、オンボーディングが求められる背景や課題を整理し、オンボーディングツールの導入メリットや選び方を詳しく解説します。
また、厳選したおすすめのオンボーディングツール8選もご紹介するので、自社に最適なツール選びの参考にしてください。
目次
オンボーディングとは?
オンボーディングとは、新入社員が企業文化や業務にスムーズに適応し、早期に活躍できるようにするためのプロセスです。企業ごとに方法は異なりますが、一般的には以下のような取り組みが含まれます。
- 企業理念やミッションの共有:会社の価値観や方向性を理解し、一体感を持ってもらう
- 業務の基礎教育:ツールの使い方や業務フローの説明を行い、スムーズに業務を開始できるようにする
- 社内コミュニケーションのサポート:上司や同僚との関係構築を促進し、相談しやすい環境を作る
特に近年、リモートワークの普及や働き方の多様化により、対面での指導が難しくなっています。そのため、デジタルツールを活用したオンボーディングの需要が高まっています。
従来の新入社員研修は、入社後の一定期間に一括で行われるケースが一般的でした。しかし、オンボーディングは研修とは異なり、長期的な視点で継続的にサポートを行う点が特徴です。
オンボーディングが必要とされる背景
近年、企業がオンボーディングに力を入れる理由として、「人材流動性の高まり」と「離職率の増加」が挙げられます。
現代は終身雇用の概念が薄れ、多様なキャリアパスが選択されるようになりました。特に、転職市場の拡大やフリーランスの増加により、人材の流動性が高まっているのです。
このような環境の中で、企業が優秀な人材を定着させるのはこれまで以上に難しくなっており、新入社員が「この会社で長く働きたい」と感じられるようなオンボーディングの重要性が高まっていると言えるでしょう。
また、新卒社員の3年以内の離職率は約30%と高い水準を維持しています。早期離職の主な原因として、「業務内容が事前のイメージと異なる」「教育・フォロー体制の不備」「社内の人間関係の希薄さ」などです。
企業にとって、採用や教育にかけたコストを回収する前に人材が離れてしまうのは大きな損失となります。そのため、新入社員の不安を軽減し、定着率を向上させる施策が求められるでしょう。
(厚生労働省「新規学卒者の離職状況(令和3年3月卒業者)」:https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000177553_00007.html)
オンボーディングの課題
オンボーディングの重要性が高まる一方で、実施にはさまざまな課題が存在します。
まず、新入社員の受け入れにおいて、教育担当者の負担が大きくなることが挙げられます。同じ内容を繰り返し説明しなければならないうえに、個々の理解度に応じたフォローも求められるのです。
さらに、業務と並行して教育を行う必要があるため、特に忙しい現場では十分な時間を確保できないケースも少なくないでしょう。
次に、オンボーディングに必要な情報が、社内のさまざまな場所に分散している点も、大きな課題です。
会社の理念や業務マニュアル、使用ツールの説明など、新入社員が必要とする情報が一元化されていないと、業務の習得に時間がかかってしまうでしょう。
さらに、オンボーディングの進捗管理が不十分だと、新入社員がどの研修を終えたのか分からなくなり、理解度にばらつきが生じます。フォローが必要な人を適切に把握できないと支援が行き届かず、早期離職につながるリスクも高まります。
オンボーディングツールを導入するメリット
オンボーディングを効率的に進めるには、オンボーディングツールの導入が不可欠です。
以下でオンボーディングツールのメリットを3つ解説します。
教育担当者の負担を軽減できる
オンボーディングツールの導入により、教育担当者の負担を大幅に軽減できます。
従来の研修では、新入社員ごとに同じ内容を繰り返し説明する必要があり、担当者の時間と労力がかかっていました。
動画コンテンツやチャットボットを活用すれば、疑問点を一旦解決できるため、教育担当者が個別対応する負担も軽減します。
さらに、進捗状況が把握できると必要なタイミングで適切なフォローが可能となり、より効率的な育成が行えるでしょう。
新入社員の自律的な学習支援が行える
新入社員が主体的に学習を進められるのもメリットです。
検索機能を備えたナレッジ共有システムにより、必要な情報を即座に取得できるため、業務の習得効率が上がるでしょう。
また、FAQ機能を充実させると、よくある質問を自動で解決できるようになります。
さらに、eラーニング機能を活用すれば、学習内容を定着させ、個々のペースに合わせた教育が可能です。
チーム全体の業務効率向上につながる
オンボーディングツールの導入は、チーム全体の業務効率向上にも役立ちます。
新入社員の学習進捗を確認しながら進められるため、上司や先輩社員が適切なタイミングでフォローを行いやすくなり、指導のムラを防げるでしょう。
また、タスク管理機能を活用すれば新入社員が何をすべきか明確にできます。
その他、1on1サポート機能を活用すれば、定期的なフィードバックを効率的に実施できるでしょう。
新入社員の不安解消やモチベーション維持につながることで、 結果としてチーム全体の生産性向上が見込めるでしょう。
オンボーディングツールの導入手順

オンボーディングツールの導入手順は以下です。
①現状の課題を明確にする
オンボーディングツールを導入する前に、まずは現状の課題を明確にすることが必要です。
どの業務が特に負担になっているのか、新入社員がどのような点でつまずいているのかを具体的に洗い出しましょう。
例えば、「研修担当者の負担が大きい」「新入社員が必要な情報を見つけにくい」「進捗管理が不透明」などの課題が挙げられます。
次に、現在のオンボーディングプロセスを整理し、どの部分をツールで改善できるのかを検討しましょう。
この段階で課題を明確にしておくと、ツール導入後の効果を正しく評価できるようになります。
②導入候補のツールを比較・検討する
現状の課題を整理したら、それを解決できるオンボーディングツールを比較・検討します。
ツールの選定では「機能」「価格」「サポート体制」などの要素を考慮し、自社に最適なものを選ぶことが重要です。
例えば、進捗管理機能が充実しているもの、学習コンテンツをカスタマイズできるもの、他の業務ツールと連携可能なものなど、企業ごとに求める機能は異なります。
可能であれば無料トライアルを活用し、実際の使用感を確認しましょう。実際の業務にどのように組み込むかを具体的にイメージしながら、導入の可否を判断します。
③社内関係者と調整し、導入計画を立てる
オンボーディングツールは、人事部門だけでなく、現場のマネージャーや教育担当者も関わるため、導入前に社内関係者との十分な調整が必要です。
ツールの導入でどのような変化が期待できるのかを共有し、スムーズに運用できる体制を整えます。
また、実際に活用するための研修やマニュアルの作成も必要です。
特に、新入社員が戸惑わずに使えるよう、ツールの操作方法や活用方法を分かりやすく伝える工夫が求められます。
導入計画をしっかりと立てられると、スムーズな運用が可能になるでしょう。
④試験運用を行う
ツールの導入はいきなり全社展開するのではなく、まずは小規模チームで試験運用を行い、問題点を洗い出しましょう。
例えば、新入社員がツールを使いこなせているか、教育担当者の負担が本当に軽減されているかなどを検証し、必要に応じて調整を行います。
試験運用の結果をもとに、機能の追加や運用方法の見直しを行い、より実用的な形へと改善を進めましょう。
この段階でしっかりとフィードバックを反映させ、本格導入後スムーズな運用ができるようにしましょう。
⑤導入後、効果測定を行い改善につなげる
オンボーディングツールを導入した後は、定期的に効果測定を行い、継続的な改善を図りましょう。
例えば、新入社員の適応スピードの向上、教育担当者の負担軽減、離職率の低下など、導入目的に応じたKPIを設定し、実際のデータをもとに評価を行います。
その結果を踏まえ、運用方法を最適化し、より効果的なオンボーディング環境を整えていきます。
また、定期的なアップデートや社内アンケートを通じて、ツールがどの程度活用されているのかを把握するのも重要です。
オンボーディングツールを選ぶ際のポイント
以下では、オンボーディングツールを選ぶ際のポイントを3つ解説します。
目的に合った機能があるか
オンボーディングツールを選ぶ際には、まず自社の課題に合った機能が搭載されているかを確認しましょう。
例えば、情報共有が課題であればマニュアルやナレッジを一元管理できる機能、進捗管理が課題の場合、研修の受講状況やタスクの進行度を確認できる機能が必要です。
また、アンケート機能や1on1ミーティングの管理機能があると、教育体制を強化できます。
新人でも使いやすいか
オンボーディングツールは、新入社員でもスムーズに活用できるかを確認しましょう。
特に、ITリテラシーが高くない新入社員でも直感的に操作できるUIが重要になります。
シンプルなデザインで視認性が高く、必要な情報にすぐアクセスできる構造になっているかを確認するとよいでしょう。
さらに、LINEのように日常的に使い慣れたツールと連携できると、新入社員のツールへの抵抗感を減らせます。
例えば、LINE公式アカウントの応答メッセージを活用すれば、よくある質問を自動で回答でき対応の効率化が可能になります。
コストパフォーマンスは適切か
オンボーディングツールを検討する際には、機能だけでなく費用面も考慮しましょう。
ツールの導入には初期費用や運用にかかるコストが発生します。
まず、初期費用については、システムの導入や環境設定にかかる費用を確認しましょう。 業務フローにカスタマイズが必要なときは、追加の開発費用が発生する場合があります。
さらに、導入後のサポート体制も重要です。例えば、無料トライアルが用意されているか、導入時の研修設定支援が受けられるか確認すると、スムーズな運用につなげられるでしょう。
【厳選】おすすめのオンボーディングツール8選
ここでは、数あるオンボーディングツールの中から厳選した8つのツールを紹介します。
- Lキャスト、ナレカン、Stock:情報共有をスムーズにしたい
- Trello:タスク管理を強化したい
- CO:TEAM:マネジメントを改善したい
- MotifyHR:エンゲージメントを向上させたい
- Onn:入社手続きを効率化したい
- ココラボ:アンケートやフィードバックを活用したい
Lキャスト
「Lキャスト」は、「Lステップ」と連携して利用するツールです。LINEと連携した自動ウェビナーツールとして、効果的なオンボーディングを実現できるでしょう。
LINEログイン認証により、参加者がどのコンテンツを視聴したかを正確に把握し、適切なフォローアップを可能にします。
また、コメントアクション機能を活用して視聴者の質問や反応に応じた自動アクションを実行し、疑問解消やエンゲージメント向上につなげられる点も強みです。
さらに、自動定期配信機能により、オンボーディングコンテンツの配信スケジュールを自由に設定でき、新入社員が段階的に学習を進められる環境を作れます。
ナレカン
ナレカンは、ナレッジ管理に特化したオンボーディングツールです。
社内の知識やマニュアルを一元管理できるため、新入社員が必要な情報をすぐに見つけられます。
特にAI検索機能が優れており、質問機能と組み合わせると業務の疑問をすぐに解決できる環境を整えられる点が特徴です。
このツールは、社内の情報が分散しやすく、必要な情報を探す手間を減らしたい企業や、業務の属人化を防ぎ、ナレッジの蓄積を促進したい企業に適しています。
Stock
Stockは、シンプルな操作性が魅力のツールで、特にITに不慣れなメンバーが多い企業に適しています。
ノート機能を活用すれば、業務マニュアルや手順書を簡単に作成・共有することができ、チーム全体での情報共有がスムーズになります。
また、メッセージ機能も備えているため、チャット感覚で気軽にコミュニケーションがとれるのもメリットです。
このツールは、直感的な操作が求められる現場や、少人数のチームでの情報共有を重視したい企業におすすめです。
Trello
Trelloは、タスク管理に優れたオンボーディングツールです。
ボード形式のインターフェースを採用しており、新入社員の進捗状況を視覚的に把握できます。
タスクの割り当てや優先順位の設定が自由に行えるため、プロジェクト単位でオンボーディングを進めたい企業には特に適しています。
また、チーム全体でリアルタイムにタスク管理ができる点も強みです。
プロジェクトごとに業務を整理したい企業や、視覚的にタスクを管理しながら進めたい企業に向いています。
CO:TEAM
CO:TEAMは、定期面談の管理やフィードバック機能を備えたツールです。
上司やメンターとの1on1を通じて目標達成をサポートし、結果やプロセスのデータを人事評価に活用して、目標管理の運用を最適化します。
また、評価者は、1on1で蓄積されたデータや目標の進捗・達成状況をそのまま評価に反映できるため、被評価者の納得感を高め、従業員の満足度を高められます。
このツールは、マネジメントを強化したい企業や、新入社員との定期的なコミュニケーションを重視する企業におすすめです。
MotifyHR
MotifyHRは、新入社員のエンゲージメント分析や適応支援を行うツールです。
社員の適応状況をデータで把握し、メンタルヘルスのサポートも提供します。
また、上司や同僚との関係性を可視化できるため、フォローが必要な社員を見逃すことなくサポートできます。
このツールは、オンボーディングの効果を定量的に測定したい企業や、新入社員の定着率向上を目指したい企業におすすめです。
Onn
Onnは、入社手続きを効率化するオンボーディングツールです。
入社者に関する各種情報(基本情報、面談内容、コミュニケーション記録など)を一箇所に集約し、担当チーム全体で情報共有できるため、人事担当者の負担を大幅に軽減できます。
また、シンプルなUIで新入社員でも簡単に扱いやすいという特徴もあります。
このツールは、入社前後のプロセスをスムーズにしたい企業や、ペーパーレス化を進めたい企業におすすめです。
Cocolabo
Cocolaboは、アクションリストやレーダーチャート機能、タイムライン、デイリーチェックシートを備えたオンボーディングツールです。
レーダーチャートでは、カテゴリー別に進捗を可視化できるため、管理者は分析の手間をかけずに新入社員の状態を把握できます。
また、タイムライン機能により、新入社員が更新した情報をリアルタイムで共有でき、チームメンバーは「いいね」やコメントでサポート可能です。
さらに、デイリーチェック機能を通じて新入社員のコンディションを把握し、必要なフォローが行えるほか、シェア機能を活用すれば、相談やサポートを求める投稿に対して適切な支援を提供できます。
このツールは、チーム全体で新入社員の成長を支援し、円滑なオンボーディングを実現したい企業におすすめです。
まとめ
今回はオンボーディングツールについて解説しました。
オンボーディングツールの導入は、新入社員の支援と教育担当者の負担軽減が同時に実現可能です。
現状を分析し、自社にあったツールを選びましょう。












-1.jpeg)