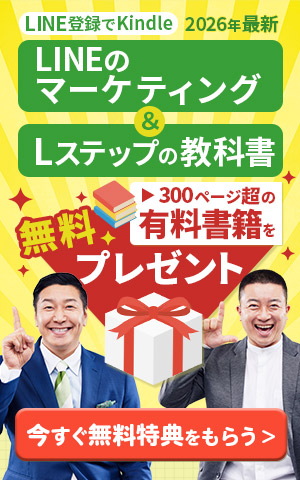スマホ1つで視聴できるオンライン講演会は、多くのユーザーと交流できるメリットがあります。
しかし、オンライン講演会を開催したくても、以下のような悩みを抱えている人も多いのではないでしょうか。
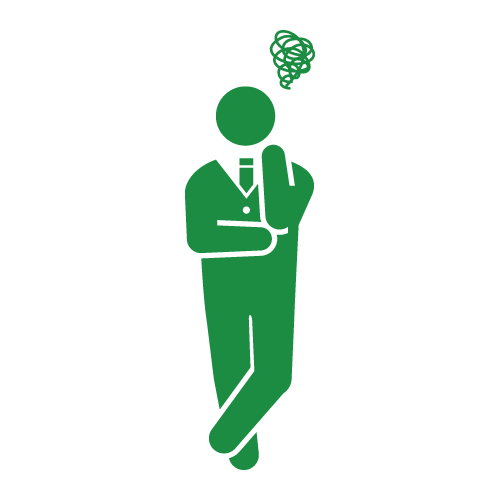
- オンライン講演会の開催方法を知りたい
- 成功させるためのコツを知りたい
- ツールが多くて選べない
この記事では、オンライン講演会の開催方法から配信ツールまで、幅広く解説します。
オンライン講演会に興味がある人は、ぜひ参考にしてみてください。
目次
オンライン講演会とは

オンライン講演会はインターネット上で開催する講演やセミナーを指します。
Webとセミナーを組み合わせて、ウェビナーと呼ばれる場合もあります。
コロナ禍で急速に普及し、今では講演会を開催する方法の1つとして定着しました。
ウェビナーはビジネスシーンだけでなく、教育や医療などの学会でも利用されています。
企業や団体が開催する以外にも、個人の開催もかんたんです。そのため、現在では多くの講演会がオンラインで開催されるようになりました。
リアル講演会とオンライン配信を組み合わせたハイブリッド型も注目されており、さらなる発展が期待されています。
オンライン講演会の種類
オンライン講演会は、ライブ配信かオンデマンド配信に分かれています。
講演を開く目的や、聴講者のニーズに合わせて配信方法を選択しましょう。
リアルタイムで進行するライブ配信
ライブ配信はあらかじめ設定した日時に、リアルタイムで講演を配信する方法です。
視聴者も発言できたり、チャットで質問できたりと、双方向のコミュニケーションによる臨場感が特徴です。
聴講者も集中力が続きやすく、最後まで活気のあるセミナーを作りやすくなっています。
反面、主催者側に求められるスキルが高く、機材や配信ツールの知識が求められます。
配信中の聴講者の対応や予期しないトラブルなど、状況に合わせた対応が必要です。
そのため、ライブ配信はミスを未然に防げるように、事前の準備が欠かせない配信スタイルといえます。
録画したセミナーを再生するオンデマンド配信
オンデマンド配信は、事前に録画した動画を配信する方法です。ライブ配信した講演会の動画を公開するケースもあります。
聴講者が自分の都合のよい時間に、講演会を視聴できる点がメリットです。
スライドや写真、テロップなどの編集を組み込んで、クオリティの高い動画を公開できます。
しかし、見やすい編集のためには時間と経費が必要です。
そのうえ、編集した動画であっても、聴講者が受け身になり飽きやすいのもデメリットです。
オンデマンド配信は、最後まで視聴してもらうための企画や、演出に工夫を取り入れた編集が重要になります。
オンライン講演会のメリット
オンライン講演会のメリットは、以下の6つです。
- 配信会場を自由に設定できる
- 会場、人件費などのコストダウンができる
- アプローチできる層を広げられる
- 講師のスケジュール調整に合わせやすい
- 資料やアンケートをデジタルで配布できる
- セミナー動画を録画して再利用できる
実際の講演会に比べると、さまざまなコスト削減が可能です。
聴講者にも、自宅から参加できるオンライン講演会ならではのメリットがあります。
例を挙げると、外出の必要がないので感染症のリスクが少なく、会場までの移動費の節約などです。
そのほかにも、地方でも参加しやすいので、都市部との情報格差を減らす効果も期待できます。
オンライン講演会のデメリット
オンライン講演会のデメリットは、以下の5つです。
- 聴講者の集中が途切れやすい
- 会場や講師の雰囲気が伝わりにくい
- 香りや食感などの情報は伝えられない
- 参加者同士の関係性が深まりにくい
- 高齢者の集客が難しい
オンラインの状況下では、伝えられる情報に限りがあります。
また、聴講者は自宅から参加している場合が多く、集中しやすい環境とはいえません。
そのため、セミナーに集中してもらえるようなコミュニケーションが必要です。
オンライン講演会の開催手順

オンライン講演会の開催手順を紹介します。
企画を立てる
まず、配信内容の軸になる講演会のテーマを決めます。
テーマに必要なポイントは、以下の3つです。
- 目的:何のために
- 対象:誰に対して
- 内容:何を伝えるのか
講演会の目標が決まったら、次の項目を考えます。
- 予算
- 講師
- スケジュール
- 所要時間
- 配信方法
初めての講演会の場合は、スケジュールは余裕を持って取り組むことをおすすめします。
誰でも最初は不明点が多く、必要な機材の操作方法、配信トラブルなどで作業が予定通りに進みません。
もし、企画が決められない場合は、興味のあるオンライン講演会に参加してみましょう。
よいアイデアが見つかるかもしれません。
開催の準備を進める
次に、スケジュールを意識しながら、開催の準備を進めます。
以下に、開催手順の一例を紹介します。
- 講師のスケジュール確保
- 会場・人材手配
- 配信機材の準備
- 集客開始
- 資料・台本の用意
- リハーサル
- リマインド
- 当日リハーサル
なるべく講師の日程調整や配信会場の手配、配信機材から優先的に押さえていきましょう。
万が一、スケジュールが合わなければ、全体の日程を調整しなければいけません。
開催に必要な人材や機材を確保できない場合は、代替案の検討が必要です。
講師が不在でも、リハーサルは必ず実施してください。配信トラブルを未然に防ぐには、リハーサルが効果的です。
開催中は進行をコントロールする
講演会の開催中は、聴講者の集中が途切れないように進行のコントロールが必要です。
講演を開催する30分前程度から配信を始めます。
開始直後は参加者へアナウンスを行い、音量の確認やタイムスケジュール、アンケートの協力をお願いしましょう。
登壇者が話し始めてから参加する聴講者も想定して、チャット欄から目を離さないようにしてください。
音声のボリュームとノイズに関するコメントは、早急に対応しないと離脱の原因になります。
また、オンライン講演会は主催者側から一方通行のコミュニケーションになりがちです。
視聴者の様子を見ながら、スケジュールに影響が出ない範囲で質疑応答を設けるなど、進行の調整も必要になります。
聴講者のアフターフォローを実施する
オンライン講演会が終了したら、聴講者へフォローを行います。
録画した動画を共有したり、使用したスライドを送付したりするなど、充実したアフターフォローが参加者の満足度を上げていきます。
聴講者の満足度や理解度など、最終的な評価を知りたければアンケートが有効です。
アンケートの回答率を上げるためには、限定の特典を用意しておくとよいでしょう。
例えば、登壇者の特別な資料やテンプレートがあれば、回答する意欲を刺激できるはずです。
参加した人は、講演会の内容だけでなく、開催前後の運営の対応も見ています。だからこそ、素早く丁寧なアフターフォローが、評価アップのポイントになるのです。
録画した動画を再利用する
講演会の配信を録画しておけば、編集して別のコンテンツとして再利用できます。
例えば、有益なセミナー動画として有料販売したり、社員教育の研修動画にしたりと活用法はさまざまです。
最近では、録画動画をライブ配信のように演出する「擬似ライブ配信」が注目されています。
講演会を録画した動画は、擬似ライブ配信と相性がよいコンテンツの1つです。
ですが、動画の著作権が講師側にある場合、無断で録画すると著作権法違反にあたる危険性があります。
そのため、外部の講師に依頼する時点で、動画の再利用について相談しておきましょう。
クオリティの高い録画コンテンツは、運用手段が多くあります。開催した講演会の趣旨に合う再利用先を探してみましょう。
オンライン講演会を成功させるポイント
オンライン講演会を成功させるためのポイントを紹介します。
企画の内容が成功のカギを握る
講演会の成功には、開催者と参加者でお互いに利益を出せる企画が必要です。
企画の内容とターゲットの要望がマッチしていれば、双方向のコミュニケーションが起きやすくなります。
逆に、企画と参加者の目的が合わなければ、どれほど質の高い講演会でも評価は高くなりません。
内容に満足した参加者なら、アンケートの回答もより正直に向き合ってくれるはずです。
正確な調査結果が集まり、次の開催に向けて実用的なフィードバックが集まります。
参加者を視野に入れた企画が、質の高い講演会を作るための基盤といえます。
配信設備の準備は念入りに行う
オンライン講演会のトラブルは、配信関係がほとんどです。
すべてのトラブルを未然に防ぐことはできません。しかし、事前準備を念入りにすれば、防げるケースが多くあります。
配信経験が浅い人は、初めて使う機材やツールばかりです。必要なパーツや関連する機材、契約プランなど、リサーチが欠かせません。
また、どんなに評判がよくても、使ってみたらイメージと違う場合も考えられます。
例えば、Bluetoothの設備は便利ですが、ノイズや遅延があったり、電波の干渉によって配信トラブルの原因になったりします。
配信設備はトラブルを前提に用意しておきましょう。当日に使えない事態も想定して、予備の機材も準備しておくと安心です。
開催前にリハーサルを行う
リハーサルは実際に講演を開く場所で行います。本番と同じ流れで実演した方が、問題点が見つかりやすくなります。
使い慣れた配信機材でも、実際の会場で同じように使えるとは限りません。
例えば、ケーブルの長さやWi-Fiの通信環境など、会場の事前情報と違う場合があります。
そのほかにも、周囲の雑音や照明の明るさなど、撮影してみなければわからないものもあります。
リハーサルは機材の動作チェックだけでなく、実際の場所で撮影や配信状況まで確認することが大切です。
聴講者のアフターフォローを早めに実施する
アフターフォローは、早めに実施すると参加者の印象がよくなります。講演直後は片付けで忙しいタイミングですが、なるべく早めの対応が必要です。
配布用の資料やアンケートは、事前準備の段階で済ませておけば、すぐに送信できます。また、聴講者の印象は、時間が経つほど薄れてしまいます。アンケートの回答率も下がる一方です。
反対に、早めにアンケートの送付や参加特典を配布するだけでも、ほかのセミナーと比べ好印象になるでしょう。
当日に上がった疑問点や、質問などにまとめて回答したPDFを送付するのも効果的です。アフターフォローは細かい作業になる分、講演会の独自性を高めるチャンスです。
難しいと思ったら、専門業者へ依頼を検討する
オンライン講演会は配信環境が必要で、リアルセミナーよりも準備する機材や設備が多くなります。
コスト削減が期待できるメリットは大きいですが、ライブ配信に関する専門的な技術が必要です。
とくに、実際の講演会とオンライン配信を組み合わせたハイブリッド型は、専門業者に依頼した方が失敗のリスクを抑えられます。
専門業者は配信だけでなく、企画段階から委託できます。ライブ配信が難しいと感じたら、専門業者に委託するのもおすすめです。
オンライン講演会に使いやすいおすすめツール7選
オンライン講演会におすすめのツールを紹介します。
予算内で企画内容に適したツールを選びましょう。
【コスパ重視】少ないコストで不特定多数に配信できる
始めに、少ない予算でも利用できるツールを紹介します。
初心者や小規模の講演会なら、コストパフォーマンス重視のツールがおすすめです。
Zoom

出典:Zoom
Zoomは企業を中心に利用率が高く、オンライン講演会でも使いやすいWeb会議システムです。
ビジネスパーソンを対象にしたセミナー向きのツールです。
有料プランに契約すれば、大人数に配信できる「Zoom Webinars」が利用できます。
チャット、アンケート、挙手、画面共有などオンライン講演会に必要な機能が充実しています。
パネリストとして外部から講師が参加できる機能もあり、主催者以外でも映像や画面共有などの操作が可能です。
講師が別会場からオンラインで参加する講演会には、便利な機能がそろったZoomをおすすめします。
Google Meet

出典:Google Meet
Google Meetは、Googleアカウントがあれば誰でも利用できる手軽さが魅力のツールです。
無料プランでも画面共有やチャットを利用できるので、小規模のセミナーにおすすめです。
有料プランも680円からと利用料金が低く設定されています。ビデオ録画がしたい場合は、Business Standardプラン以上の契約が必要です。
Googleサービスと連携できる点が最大のメリットです。
GoogleのAI「Gemini for Google Workspace」と連携すれば、AIのサポートも利用できます。
最近では、AIの併用がビジネスシーンの課題として挙げられています。Gemini for Google Workspaceは、講演会の要約などに活用できるでしょう。
YouTube
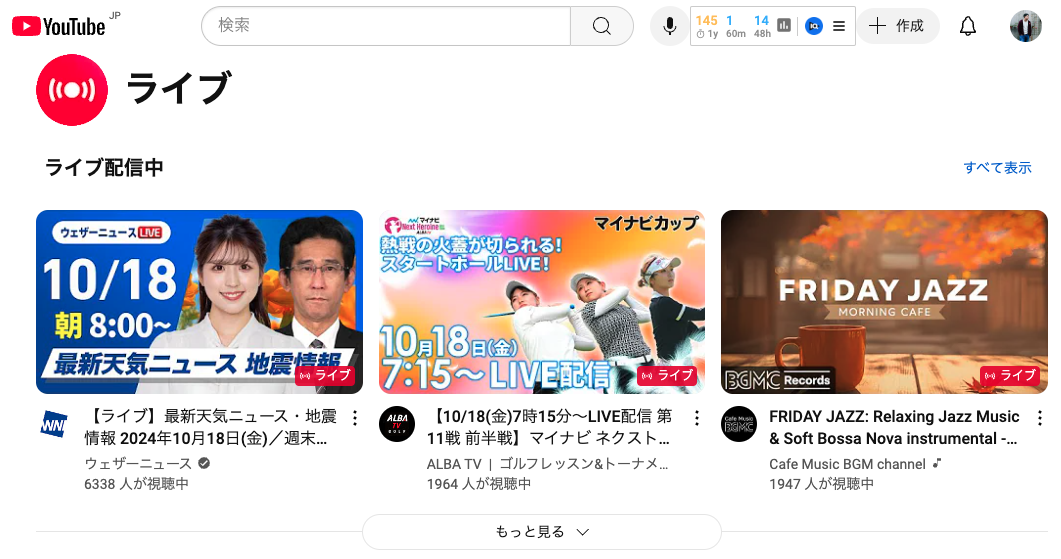
出典:YouTubeライブ
YouTubeは、トップクラスの知名度を誇る配信ツールです。
不特定多数の人に、情報を公開したい場合におすすめです。
セミナー配信用のツールではないので、ライブ配信では聴講者に発言権がありません。
コミュニケーションツールはチャットのみです。そのため、参加者と交流を深めるための施策を用意しておきましょう。
講演会のアーカイブを残しておけば、YouTubeのアルゴリズムに従って、視聴しそうなユーザーに提案してもらえます。
この拡散性の高さが、YouTube最大のメリットです。
【機能性重視】質にこだわった配信ができる
次に、機能性に優れたツールを紹介します。
企画の課題がしっかりしていたり、規模の大きい講演会を開いたりする場合は、目標達成に必要なツールを選びましょう。
Lキャスト

「L-CAST(Lキャスト)」はLINEを利用してウェビナーを自動化できる、オートウェビナーマーケティングツールです。
Lキャストは、録画動画をリアルタイム配信のように見せる、「擬似LIVE機能」があります。
動画を用意できれば、LINEのアプリ内でオンライン講演会を実施できます。
LINEなら国内の利用者が多く、あまり抵抗感なく参加できるでしょう。
そのうえ、聴講者の行動履歴がデータとして残せるのも、Lキャストの強みです。講演後のアンケート結果も回答者ごとに残せるので、質の高いアフターフォローができます。
Lキャストの利用には、LINE公式アカウントと拡張ツール「Lステップ」の契約が必要です。
V-CUBE セミナー

出典:V-CUBE セミナー
V-CUBE セミナーは、サポート体制が充実している配信ツールです。
スタジオ手配から台本作成、配信スタッフまで、リアルタイム配信に必要な準備にすべて対応してくれます。
複数の著名人を招待する講演や、企業の大規模な講演におすすめです。リアルセミナーとオンライン配信を同時に行うハイブリッド配信にも対応できます。
しかし、金額が高額なので、企画段階で予算組みが必要です。
興味がある人は、採用前にデモ体験をおすすめします。公式サイトから申し込み可能です。
EventHub

出典:EventHub
EventHubは、ウェビナー運営に必要な機能がそろったイベント運営ツールです。
チケットの販売や参加者管理、動画配信からアンケートまで、1つのツールですべて管理できます。
さらに、参加者同士のマッチング機能が最大の特徴です。これにより、オンラインイベントの欠点だった交流不足を解消しました。
協賛企業の紹介ページ作成や担当者とWeb面談などが可能で、展示ブースがオンライン上で再現されています。
参加者もプロフィールを登録しておけば、名刺交換や交流など人脈づくりにも利用できます。
マッチング機能が充実のEventHubは、オンラインイベントの差別化に悩んでいる人に、おすすめのツールです。
Adobe Connect

Adobe Connectは、画面レイアウトのカスタマイズ性が高い配信ツールです。
変更したレイアウトをテンプレートとして複数保存して、進行に合わせながら最適なレイアウトを表示できます。
例えば、資料公開用や質疑応答用のレイアウトを用意すれば、進行にメリハリが出せるでしょう。
また、サポート機能はウェビナー初心者でも活用しやすい内容です。
用意されたテンプレートに画像やテキストを埋め込むだけで、告知ページや通知メールがかんたんに作成できます。
リマインドも設定できるので、ツール内でメールの事前準備ができる便利な機能です。
ブランドイメージを大切にしたい新商品発表会のような企画なら、Adobe Connectがおすすめです。
オンライン講演会のアフターフォローはLキャストがおすすめ
今回は、オンライン講演会の開催方法や成功のポイント、セミナーツールを紹介しました。
オンライン講演会は開催して終わりではなく、アフターフォローまで実施しましょう。
もし、アフターフォローを充実させたい場合は、Lキャストがおすすめです。
この記事を参考にして、企画からアフターフォローまで充実したオンライン講演会を開催してみてください。











-1.jpeg)